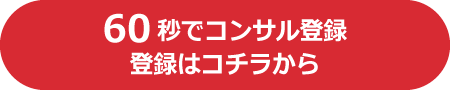フリーランスにおすすめの健康保険は?種類や保険料を抑える方法を解説

最終更新日:2025/03/06
作成日:2018/02/23
「フリーランスの国民健康保険はいくら?」「健康保険には入らなくてもいい?」と疑問に思っていませんか。
フリーランスの健康保険加入は必須であり、保険料は加入する制度によって変わります。国民健康保険が高すぎると感じているフリーランスや個人事業主の方は、健康保険制度について理解を深めて、支払い計画を立てることが大切です。
フリーランスが加入できる健康保険の種類や、国保以外の選択肢を解説しています。
目次
■フリーランス向けの健康保険
(1)国民健康保険
(2)前職の健康保険を任意継続
(3)国民健康保険組合
(4)家族の扶養へ入る
■健康保険料を安く抑える方法
(1)国民健康保険免除や減免制度の活用
(2)社会保険料控除の活用
(3)国民健康保険組合に入会
(4)青色申告特別控除を活用
(5)法人化
■【国民健康保険以外】フリーランスにおすすめの組合・団体とは
(1)Webデザイナーなら「日本イラストレーション協会」
(2)IT系ライターなら「日本デジタルライターズ協会」
(3)その他の業種なら「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」
社会保障の不安も多いフリーランス

会社員だった時代にはあまり意識していなかったということも少なくない、社会保険や保障の恩恵。フリーランスになると、そのありがたみをいやというほど痛感させられる機会がたびたびあるものです。
たとえば、健康保険や年金の保険料は半額を会社が負担してくれますし、年金は国民年金に加えて厚生年金という2階建てです。
病気やけがで仕事を休むことになったときにも、会社員には所得補償として平均日額の3分の2相当額が支給される傷病手当金がありますが、自営業の加入する国民健康保険では何の所得補償もありません。
自身や家族がお子さんを生んだ場合に出産育児一時金を受け取れるのは自営業も変わりませんが、無給で会社を休む場合の保障である出産手当金も、受け取れるのは会社員のみです。
少ない保険料負担で保障も手厚い会社員に比べて、自営業は高額な国民健康保険に加入を余儀なくされ、年金も国民年金のみ。
そのようなことを理解したうえでフリーランスになったという方でも、最初に社会保険料の負担の大きさを実際に目にしたときには、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そして、万一何かあって仕事ができなくなっても何の保障もないということが大半です。
個人で仕事するフリーランスは、多少なりとも仕事の多寡や活動の継続に不安な気持ちを抱えているものです。加えて保険料の負担が大きくのしかかり、保障も手薄ということになると、不安はさらに大きくなってしまいます。
そうしたなかで助けになるのが、フリーランスも加入できる“組合”です。
☆あわせて読みたい
『フリーランス人材の悩みとは?業務委託の雇用形態とメリットデメリットを解説』
『フリーコンサルタントは副業でも稼げる?単価・種類・注意点を解説!』
健康保険とは?

健康保険とは、病気やケガ、出産、死亡などの事態に備えるための制度です。
日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての国民に健康保険への加入が義務付けられています。つまり、フリーランスも何かしらの健康保険への加入が必要です。
加入者は日頃から保険料を支払うことで、いざという時の費用負担を軽減させることができます。
フリーランス向けの健康保険
ここでは、フリーランスにおすすめの健康保険を紹介します。個人によって最適な保険が異なるので、収入額や家族の状況などを見て加入することが大切です。
(1)国民健康保険
国民健康保険は、75歳未満の自営業者やフリーランスが加入する保険制度です。退職後に会社の保険を任意継続せず脱退した場合も、国民健康保険に加入します。
保険料は世帯の加入人数や年齢、収入額などをもとに決定しますが、計算方法や料率は自治体によって異なります。なお、保険料の支払いは会社員等が加入する健康保険と異なり、全額自己負担です。
(2)前職の健康保険を任意継続
会社員からフリーランスに転身した方の場合、勤めていた会社の健康保険への加入を任意で継続できる可能性があります。
以下の要件を満たしている方は、退職してから「2年間」は加入を継続可能です。
- ・資格喪失日の前日までの加入期間が2ヶ月以上あること
- ・資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
ただし、会社員の頃とは違い、会社が保険料の半額を負担してくれるわけではないので注意が必要です。
(3)国民健康保険組合
国民健康保険組合(国保組合)とは、特定の職業の人が加入できる健康保険です。例えば、文芸美術国民健康保険組合は、文芸・美術・映画・写真などに関する仕事をしている人を加入対象にしています。
国民健康保険組合の保険料は固定料金制のケースが多く、収入によっては国民健康保険よりも負担額を抑えられる可能性があります。
国民健康保険組合にはさまざまな種類があり、それぞれの組合によって加入できる職業の方が異なります。
(4)家族の扶養へ入る
フリーランスは、家族の扶養に入ることも可能です。ただし、扶養に入るには、年収130万円未満でなければいけません。
フリーランスが健康保険に加入しないとどうなる?
フリーランスを含むすべての国民は、健康保険に加入する必要があります。日本では「国民皆保険制度」が採用されているためです。
加入手続きを行わなかった場合でも、遡って保険料を納付しなくてはいけません(最大2年間の保険料が請求されます)。会社員からフリーランスに転身し、国民健康保険等に加入する場合は、退職後「14日以内」に加入手続きを行いましょう。
フリーランスが保険料を払えない場合
それでは、保険料を支払えなかった場合はどうなるのでしょうか?
国民健康保険には、保険料を支払えない方を対象にした軽減制度が用意されています。軽減制度を利用する場合は、自治体に申請を行う必要があります。
世帯の所得の合計額によって軽減割合が異なるため、お住まいの自治体にご確認ください。
健康保険料を安く抑える方法
(1)国民健康保険免除や減免制度の活用
保険料の支払いが困難な場合は、国民健康保険料の軽減・減免制度を利用することが可能です。一定の基準を満たしている方は、保険料が軽減・減免されます。
制度はいくつかの種類に分けられます。
- ・災害減免
- ・生活困窮減免
- ・収入減少減免
- ・給付制限減免
上記の制度を利用するためには、保険料の納期限内に申請する必要があります(災害減免と給付制限減免は除く)。
(2)社会保険料控除の活用
社会保険料控除とは、支払った社会保険料について所得控除を受けられる制度のことです。国民健康保険の保険料をはじめ、介護保険料や労働保険料、国民年金基金の掛金なども対象に含まれます。
確定申告を行う際に社会保険料控除の項目を記入し、控除証明書とともに申告書を提出してください。社会保険料控除の詳細については、国税庁の公式サイトで確認しましょう。
参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」
☆あわせて読みたい
『フリーランスにおすすめの社会保険一覧!会社員との違いとは』
(3)国民健康保険組合に入会
国民健康保険組合に入会することで、保険料を抑えられる可能性があります。
国民健康保険の保険料は収入額に応じて決まりますが、国民健康保険組合の保険料は固定料金制になっていることが多いです。収入によっては、国民健康保険組合に加入した方が負担を軽減できるでしょう。
(4)青色申告特別控除を活用
青色申告特別控除とは、所得金額から55万円(もしくは65万円)、または10万円を控除できる制度のことです。
青色申告を行う場合は、事業開始日から「2ヶ月以内」、もしくは「1月1日〜3月15日」の間に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
3月15日の期限を過ぎた場合、青色申告を行えるのは翌年からになるため、期限内に提出するようにしてください。
(5)法人化
法人化することで保険料を抑えられるわけではないですが、将来受け取れる年金が多くなります。
フリーランス・個人事業主の場合、「国民年金」と「国民健康保険」に加入するのが一般的です。一方、法人化した場合は「厚生年金」と「協会けんぽ」に加入します。
年金保険料は法人化した方が負担が大きくなります。健康保険の保険料は大きく変わりませんが、協会けんぽの方が給付が多いです。
☆あわせて読みたい
『個人事業主と法人、税金はどちらがお得?』
【国民健康保険以外】フリーランスにおすすめの組合・団体とは

“組合”に加入することには、健康保険料の軽減だけではなく、さまざまなメリットがあります。仕事の斡旋を受けたり、イベントで人脈を広げたりといったことが可能になれば、本業への好影響も期待できます。
“組合”は安心してフリーランスとして働き続けていくことを助けてくれる存在になるかもしれません。
(1)Webデザイナーなら「日本イラストレーション協会」
イラストレーション関連の業種、グラフィックデザインやWebデザインなどに従事するデザイナー、漫画家といった業務に従事する法人および個人事業主が加入できるのが、日本イラストレーション協会(JILLA/ジャイラ)です。
日本イラストレーション協会は、「プロである組合員同士が集まり、より大きな団体として活動する事でスケールメリットを活かし、お互いの事業を『互助』」することなどを使命として掲げています。
加入すると、連携したセミナーや講座を割引価格で受講することができたり、文具や画材などを割引価格で購入することが可能になったりします。
そして大きいのは、文芸美術国民健康保険組合の加盟団体であるということ。日本イラストレーション協会の組合員が、確定申告書などで条件を満たす事業を行なっていると証明できれば、文芸美術国民健康保険組合に加入することができるのです。
そのほかには、お得な保険料で所得補償保険に加入できる制度もあります。所得補償保険に加入すると、病気やけがで仕事ができなくなった場合に一定期間内の収入源を補う補償を受けることができ、補償の薄いフリーランスにとっては心強い味方になるでしょう。
(2)IT系ライターなら「日本デジタルライターズ協会」
近年増加しているライター業のなかでも、IT分野に関するライティングに従事する個人事業主が対象となっているのが、日本デジタルライターズ協会です。
日本デジタルライターズ協会も文芸美術国民健康保険組合の加盟団体であり、会員になることによって文美国保に申し込む資格を得ることができるということになります。
日本デジタルライターズ協会に加入するためには、審査に加えて、協会の理事1人または入会審査委員1人の推薦が必要です。
また、日本デジタルライターズ協会では、ライター同士の情報交換やセミナーの企画などを予定しているとしています。
会員でなくても参加できる勉強会も企画されることがあり、2017年に実施された「フリーランスライターのための確定申告 勉強会2017」では多くの参加者が集まりました。
(3)その他の業種なら「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」
最近注目を集めているのが、「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(フリーランス協会)」です。フリーランス協会は業種を問わず、フリーランスやパラレルワーカーとして働いている方であれば対象となります。
フリーランス協会は文美国保の加盟団体ではないため、健康保険加入のメリットは得ることができませんが、所得補償や賠償責任補償を受けられる保険に会員価格で加入できます。
福利厚生サービスを利用できたり、コワーキングスペースや会計ツールなどの提携サービスを割引価格で利用できるようになったりすることがメリットです。
※みらいワークスが、フリーランス協会と共催したイベントはこちら
まとめ
本記事では、健康保険の種類やフリーランスが加入できる健康保険の選択肢について詳しく解説しました。
フリーランスには「国民健康保険に加入」「前職の健康保険を任意継続」「国民健康保険組合に加入」といった選択肢があります。また、条件を満たせば家族の扶養に入り、被扶養者家族として健康保険に加入することも可能です。
「フリーコンサルタント.jp」では、フリーランスコンサルタント向けの案件紹介や、独立支援などフリーランスの方に役立つサービスを提供しています。会社員からフリーランスとして独立を検討している方はぜひ会員登録をご検討ください。
→→転職を検討中の方はコンサルネクスト.jpで無料登録
→→フリーランスの方はこちらからコンサル登録
(株式会社みらいワークス FreeConsultant.jp編集部)
◇こちらの記事もオススメです◇