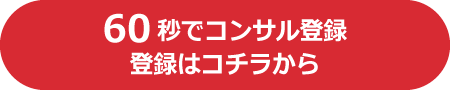フリーランス・個人事業主の確定申告のやり方は?経費になるものの例も紹介

最終更新日:2026/02/17
作成日:2019/09/30
フリーランスや個人事業主として活動する場合、必ず行わなければいけない税務上の手続きが「確定申告」です。事業収入が48万円を超えるとき、副業収入が20万円を超えるときなど、一定の条件に該当すれば必ず行う必要があります。
この記事では、確定申告の基礎知識から実践的なノウハウまで、初めての方にもわかりやすく解説します。期限や税金の仕組み、経費として認められるものなど、知っておくべきポイントをしっかり押さえていきましょう。

< 監修者プロフィール >
安松 綾菜(やすまつ あやな)
公認会計士・税理士。2020年有限責任あずさ監査法人入社後は、大手製造小売業を中心に法定監査、IPO支援業務、ファンド監査業務等に従事する。
税理士法人への転職後、2023年に独立。tokumo会計事務所として、税務顧問、クラウド会計導入支援、経理・内部統制支援などのサービスを提供している。同志社大学商学部卒業。
tokumo会計事務所:https://tokumo-cloud.com/
※申請に関する詳細は、必ず国税庁のホームページなど該当機関の情報をご確認ください。
目次
■確定申告とは?
税金を確定させるために行う
確定申告によって影響を受ける税金
■確定申告が必要なフリーランス・個人事業主の条件
副業所得20万円超えの会社員
事業収入48万円超えのフリーランス・個人事業主・自営業
■確定申告をしないとどうなる?
税金のペナルティ
社会的なペナルティ
■フリーランス・個人事業主が使える確定申告の種類
簡単にできる「白色申告」
節税効果の高い「青色申告」
■フリーランス・個人事業主の確定申告のやり方
1.開業届の提出・青色申告の申請
2.帳簿付け
3.確定申告書の作成
4.毎年定められた期間に提出・納税
5.書類・帳簿を保管
■青色申告の注意点
原則は発生主義
現金主義が認められる条件
■フリーランス・個人事業主におすすめの会計ソフト
やよいの青色申告オンライン
freee会計
タックスナップ
■確定申告時に経費になるもの・ならないもの
認められやすい経費の例
認められにくい経費の例
■フリーランス・個人事業主の確定申告に関する質問
年収100万円以下でも、確定申告は必要ですか?
扶養内でフリーランスとして働いていても、確定申告は必要ですか?
赤字でも確定申告は必要ですか?
赤字はずっと繰り越せますか?
会社に年末調整をしてもらっていない場合、確定申告は必要ですか?
為替取引などによる赤字は、事業収入の黒字と相殺できますか?
確定申告とは?

確定申告は、フリーランスや個人事業主にとって重要な税務手続きの一つです。
一度理解してしまえば難しくはありませんが、初めての方は「何のために行うのか」「どの税金に影響があるのか」をしっかり把握することが大切です。
税金を確定させるために行う
確定申告は、1年間の収入や経費を計算して、納めるべき税金の額を確定させる手続きのことです。会社員の場合、通常は会社が年末調整で手続きを代行してくれますが、フリーランスや個人事業主の場合は自分で行う必要があります。
毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年分の確定申告を行います。2月16日、3月15日が祝日・休日の場合は翌日にずれるため、令和7年(2025年)分の確定申告期間は、2月16日(月)から3月16日(月)です。
確定申告をすることで、経費を差し引いた実際の利益に応じた適切な税額を計算できます。また、医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を受けると、納税額を適正に調整できます。
確定申告によって影響を受ける税金
確定申告では、申告の内容によって、いくつかの税金が影響を受けます。初めて確定申告をする方は、一つの申告内容が複数の税金の計算に影響することを理解しておくことが重要です。
所得税・復興特別所得税
まず、所得税と復興特別所得税が影響を受けます。どちらも1年の所得に対してかかる国税であり、所得税の税率は所得の5~45%、復興特別所得税の税率は所得税額の2.1%です。
住民税(所得割)
住民税は、市区町村と都道府県に納める税金です。「所得割」と「均等割」に分かれており、確定申告によって影響を受けるのは「所得割」です。
所得割の税率は所得の10%で、そのうち6%が市民税、4%が都道府県民税が基準となっています。実際には各自治体が税率を定めているため、住んでいる地域によって納める金額は異なります。
事業税(一定の事業所得がある場合)
事業税には、個人事業税と法人事業税があります。個人事業税は、文字通り事業を行う個人にかかる都道府県税です。個人事業主やフリーランスの人でも、年間所得が290万円以上の場合は納めなければなりません。
業種によって税率が異なるため、自分が行っている仕事の業種と税率を確認しておきましょう。例えば、コンサルタント業や公認会計士業などは5%と定められています。
国民健康保険料
国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料も影響を受けます。税率は住んでいる地域によって異なりますが、40歳未満は「(所得-43万円)×8%」、40歳以上は「(所得-43万円)×10%」の計算式でざっくりとわかります。
確定申告が必要なフリーランス・個人事業主の条件
フリーランスや個人事業主として活動する場合、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。自身が確定申告の対象になるかどうか、条件を正しく理解しておきましょう。
副業所得20万円超えの会社員
会社員の方でも、副業による所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。この場合、本業の給与所得と副業の事業所得を合算して申告します。
例えば、会社員として働きながら休日にフリーランスとして仕事をしている場合や、本業とは別にWebライターやイラストレーターとして収入を得ている場合が該当します。
副業所得が20万円以下でも、給与収入が2,000万円を超えている人も確定申告が必要です。
事業収入48万円超えのフリーランス・個人事業主・自営業
事業収入が年間48万円を超えるフリーランスや個人事業主は、確定申告が必要です。フリーランスとして専業で活動している場合はもちろん、個人事業主として店舗やオフィスを構えている場合も該当します。
さらに、インターネットを通じて商品販売やサービス提供を行う場合や、クラウドソーシングなどで案件を受注している場合も確定申告の対象となります。
収入が48万円を超えても必要経費を差し引いた所得が48万円以下になる場合でも、申告が必要となる点に注意しましょう。
また、赤字(所得がマイナス)の場合でも申告を行うことで、その赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。所得税の納付が発生しない場合でも、住民税や国民健康保険料の計算のために申告が必要となる場合があります。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告とは法律で定められた義務であり、対象となる方が申告を怠ると、様々なペナルティが発生します。納税者としての責任を果たし、安定した事業運営を続けるためにも、期限内の確定申告は必須です。
税金のペナルティ
決められた期限までに確定申告を行わないと、追徴課税に加えて重い金銭的なペナルティが課されます。期限内に申告・納税を行わなかった場合、以下のペナルティが発生します。
- ・無申告加算税:納めるべき税金の15~30%
- ・延滞税:納めるべき税金に対して年2.4~14.6%
- ・重加算税:納めるべき税金の35~40%
社会的なペナルティ
税金面のペナルティだけでなく、事業活動にも大きな支障が出る可能性があります。
住宅ローンが組めない
住宅ローンを組む際、金融機関は融資審査の重要な判断材料として確定申告書を使用します。確定申告を行っていない場合、収入を証明できず、住宅ローンの審査に通らない可能性が高くなります。
年金や健康保険の給付に影響
国民年金や国民健康保険の保険料は確定申告の所得額をもとに決定されます。適切な申告を行わないと、将来の年金受給額が減少したり、保険料が実際の所得額より高く設定されたりする可能性があります。
取引先からの信用低下
取引先との関係にも影響が及ぶ可能性があります。大口の取引や契約を行う際に確定申告書の提出を求められることが多く、確定申告を行っていない場合、取引を断られるなど信用面でのリスクが生じます。
フリーランス・個人事業主が使える確定申告の種類
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。申告方法の選択は、将来の税負担や事業運営に大きく影響するため、それぞれの特徴をしっかり理解しておく必要があります。
簡単にできる「白色申告」
白色申告は、簡易な記帳で申告できる方法です。日々の収入と経費を記録した出納帳があれば申告が可能で、特別な手続きも必要ありません。
ただし、所得控除の上限が10万円と低く、赤字の繰り越しもできないため、事業規模が大きくなるにつれてデメリットが目立ってきます。
節税効果の高い「青色申告」
青色申告は、複式簿記での記帳が必要となりますが、大きな節税効果が期待できる申告方法です。最大65万円の所得控除を受けられるほか、事業で生じた赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。
また、事業専従者である家族に支払う給与も経費として認められるため、世帯全体での節税も可能です。青色申告を選択する場合は、事前に税務署への届出が必要です。会計ソフトを利用すると、複式簿記の知識がなくても正確に記帳できます。
フリーランス・個人事業主の確定申告のやり方

確定申告は、一連の手順に従って進めていく必要があります。特に初めて確定申告を行う方は、手順を飛ばしたり、期限に間に合わなかったりすることのないよう、しっかりと準備を進めることが大切です。
ここでは、確定申告の手順を5つのステップに分けて、初めての方でも迷わないよう解説していきます。
1.開業届の提出・青色申告の申請
事業を始める際は、まず開業届を提出する必要があります。開業届は事業開始から1ヶ月以内に、所轄の税務署に提出します。
青色申告を選択する場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」も提出しましょう。なお、開業初年度に青色申告を行う場合は、開業から2ヶ月以内の申請が必要です。
2.帳簿付け
日々の取引を正確に記録することが確定申告の基本となります。収入や経費を記録する帳簿には以下のようなものがあります。
- ・現金出納帳:現金の収入・支出を記録
- ・売掛帳:得意先との取引を記録
- ・買掛帳:仕入先との取引を記録
- ・経費帳:事業に関係する支出を記録
- ・固定資産台帳:パソコンなど高額な備品を記録
3.確定申告書の作成
1年間の収入と経費をまとめ、確定申告書を作成します。申告書の作成方法は主に3つあります。
会計ソフトを利用する
会計ソフトを利用する方法は、初めて確定申告を行う方に特におすすめです。freeeややよいの青色申告といった会計ソフトでは、日々の収入や経費を入力するだけで自動的に仕訳が行われ、確定申告書も作成されます。
さらに、領収書をスマートフォンで撮影して保存できる機能や、取引データを自動で取り込める機能も備わっているため、確定申告の手間を大幅に削減できます。
国税庁のホームページで作成する
国税庁のホームページで作成する方法は、会計の基礎知識がある方向けです。国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って必要事項を入力していくことで、確定申告書を作成できます。
会計ソフトと比べると手間はかかりますが、利用料金は無料です。また、前年の申告データを引き継ぐこともできるため、2年目以降の申告はよりスムーズに行えます。
税理士に依頼する
税理士に依頼する方法は、時間的な余裕がない方や、複雑な確定申告が必要な方におすすめです。税理士は税務のプロフェッショナルとして、確定申告書の作成から税務調査への対応まで、幅広くサポートしてくれます。
また、経営面のアドバイスも得られるため、事業の成長にもつながります。ただし、顧問料や申告代行費用が発生するため、事業規模や予算と相談しながら検討するようにしましょう。
4.毎年定められた期間に提出・納税
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日から3月15日まで(祝日・休日の場合は翌日)です。提出方法は、以下の2通りがあります。
e-Taxでオンライン提出
e-Taxでのオンライン提出は、パソコンやスマートフォンから24時間いつでも申告できる便利な方法です。マイナンバーカードがあれば、ICカードリーダーやスマートフォンを使って手続きが可能です。
マイナンバーカードを持っていない場合でも、税務署で事前にID・パスワードを取得すれば利用できます。最近では多くの会計ソフトがe-Taxと連携しており、ソフト上で作成した申告書を直接送信することも可能です。
税務署に直接持参
税務署への直接持参は、対面で不明点を確認できる確実な方法です。ただし、確定申告期間中は税務署が大変混雑するので、長時間待つ可能性があります。
また、税務署の窓口は平日の8:30から17:00までしか開いていないため、仕事をしている方は時間の調整が必要です。ただし、確定申告期間中は日曜日に開庁している税務署も一部あります。
納税は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日までに行います。分割納付や延納の制度もあるので、必要に応じて税務署に相談しましょう。
5.書類・帳簿を保管
確定申告に関する書類や帳簿は、法定保存期間である7年間保管する必要があります。保管が必要な主な書類は以下の通りです。
- ・確定申告書の控え
- ・帳簿類(現金出納帳、売掛帳など)
- ・請求書や領収書などの証憑書類
- ・取引に関する契約書
- ・給与支払い関係の書類
青色申告の注意点
青色申告は大きな所得控除が受けられる一方で、正確な記帳と適切な処理が求められます。特に収入と経費の計上時期については、明確なルールがあります。
原則は発生主義
青色申告では、原則として発生主義による記帳が求められます。発生主義とは、実際の現金の収支に関係なく、収入や経費が確定した時点で記帳する方法です。
例えば、12月に仕事を完了して請求書を発行し、入金が翌年1月になった場合、12月の収入として計上します。
同様に、12月に経費が発生し、支払いが翌年1月になった場合も、12月の経費として計上する必要があります。そのため、売掛金や買掛金の管理が重要です。
現金主義が認められる条件
一定の条件を満たす個人事業主は、現金主義による記帳が認められています。現金主義では、実際に現金の収支があった時点で記帳を行います。以下の条件をすべて満たす場合、現金主義を選択可能です。
- ・前々年分の不動産所得・事業所得の合計が300万円以下の小規模事業者である
- ・青色申告承認申請書を提出している
- ・現金主義による記帳を選択する旨を記載した届出書を提出している
フリーランス・個人事業主におすすめの会計ソフト
確定申告を効率的に行うためには、会計ソフトの活用が有効です。ここでは、特に人気の高い3つの会計ソフトについて、それぞれの特徴を解説します。
いずれのソフトも無料の試用期間があるため、実際に使ってみて自分に合ったものを選ぶのがおすすめです。
やよいの青色申告オンライン
やよいの青色申告オンラインは、30年以上の実績を持つ老舗会計ソフトの提供元が開発したクラウドサービスです。
初心者向けの分かりやすい操作性が特徴で、確定申告の経験がない方でも安心して利用できます。基本的な帳簿作成機能に加え、以下のような特徴があります。
- ・スマートフォンで撮影した領収書を自動で読み取り、経費として登録
- ・キャッシュレス決済との連携で、支出データを自動取得
- ・確定申告書や青色申告決算書を自動作成
- ・税理士に相談できるサポートプランも用意
freee会計
freee会計は、クラウド会計ソフトの代表的なサービスとして多くのユーザーに選ばれています。銀行口座やクレジットカードとの連携機能が充実しており、自動で取引データを取り込めることが最大の特徴です。
主な機能として以下が挙げられます。
- ・請求書の作成から入金管理まで一元化
- ・AIが取引内容を自動で仕訳
- ・確定申告書類を自動作成し、e-Taxで直接送信可能
- ・経営状況を分かりやすくグラフ化
タックスナップ
タックスナップは、個人事業主やフリーランス向けに特化した会計ソフトです。シンプルな機能と低価格が特徴で、小規模事業者に適しています。以下のような特徴があります。
- ・領収書をスマートフォンで撮影するだけで経費登録
- ・収入と経費の管理に特化したシンプルな機能
- ・クレジットカードや電子マネーとの連携も可能
- ・リーズナブルな料金設定
確定申告時に経費になるもの・ならないもの
事業の経費を適切に計上することは、確定申告の重要なポイントです。経費として認められる範囲を正しく理解し、適切に処理することで、適正な納税額を算出できます。
認められやすい経費の例
事業との関連性が明確で、一般的に経費として認められやすい項目には以下のようなものがあります。
旅費交通費
旅費交通費は、取引先への訪問や商談、セミナー参加などビジネス目的の移動に伴う交通費や宿泊費が対象です。新幹線、飛行機、タクシー代なども、業務上の必要性が説明できれば経費として認められます。
取引先との飲み会
取引先との会食費は、取引関係の維持・促進を目的とした場合、交際費として経費計上が可能です。ただし、参加者や目的を記録し、領収書を保管しておく必要があります。
会議費
会議費は、社内ミーティングや勉強会での飲食費、会議室の利用料が該当します。リモート会議を含む打ち合わせに必要な費用は、経費として認められます。
通信費
通信費は、事業用の携帯電話代やインターネット料金が対象です。プライベートとの使用区分が明確であれば、事業使用分を経費として計上できます。
資料購入
資料購入費は、業務に関連する書籍、雑誌、オンライン教材などの購入費用が該当します。スキルアップや情報収集に必要な費用として認められます。
オンラインツール利用料
オンラインツール利用料は、業務に使用するクラウドサービスやソフトウェアの利用料が対象です。会計ソフト、グラフィックツール、Web会議システムなどの月額料金を経費計上できます。
家賃
家賃は、事業用のオフィスや作業場として使用している場合、経費として認められます。自宅の一部を事業に使用している場合も、使用面積の割合に応じて経費計上が可能です。
認められにくい経費の例
以下の項目は、原則として経費として認められないか、認められるためには特別な条件が必要です。
美容代
ヘアカットやエステ、化粧品代など、個人の身だしなみに関する美容代は通常経費として認められません。ただし、美容師やメイクアップアーティストなど、職業上必要不可欠な場合は例外として認められることがあります。
衣服代
スーツやビジネスシューズなど、一般的な衣服の購入費用は経費として認められません。ただし、特殊な作業着や制服など、事業専用の衣服は経費として計上できます。
スポーツジム代
スポーツジム代は、健康維持のための費用は私的な支出とみなされ、原則として経費として認められません。ただし、スポーツインストラクターなど、職業として必要な場合は例外として認められる可能性があります。
フリーランス・個人事業主の確定申告に関する質問
確定申告について、フリーランスや個人事業主の方が抱きやすい疑問に回答します。
年収100万円以下でも、確定申告は必要ですか?
事業収入が48万円を超える場合は、年収が100万円以下であっても確定申告が必要です。
ただし、必要経費を差し引いた所得が48万円以下になる場合でも、記録を残し申告することをおすすめします。申告をすることで、収入の証明が可能になり、将来的な融資や契約の際に役立つケースがあります。
扶養内でフリーランスとして働いていても、確定申告は必要ですか?
家族の扶養に入っている場合でも、事業収入が48万円を超えると確定申告が必要です。
また、確定申告により所得が確定することで扶養から外れる可能性があるため、健康保険や住民税についても事前に確認しておくことが重要です。
赤字でも確定申告は必要ですか?
必須ではありませんが、申告をすることで以下のようなメリットがあります。
- ・赤字を翌年以降に繰り越すことができる
- ・給与所得がある場合、赤字分を給与所得から差し引ける
- ・事業実態の証明として、金融機関等に提出できる
赤字はずっと繰り越せますか?
青色申告の場合、赤字は最長3年間繰り越すことができます。例えば、2024年に発生した赤字は、2025年から2027年までの黒字と相殺することが可能です。ただし、白色申告の場合は赤字の繰り越しはできません。
会社に年末調整をしてもらっていない場合、確定申告は必要ですか?
年末調整を受けていない場合は、原則として確定申告が必要です。給与収入のみの場合でも、年末調整を受けていない場合は、所得税の精算のために確定申告を行う必要があります。
また、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。
為替取引などによる赤字は、事業収入の黒字と相殺できますか?
為替取引やFX取引による損失は、原則として事業所得の黒字とは相殺できません。これらは申告分離課税の対象となる雑所得や先物取引に係る雑所得として扱われ、事業所得とは区分して計算する必要があります。
ただし、為替取引が事業の一環として行われている場合は、税務署に相談することをおすすめします。
まとめ
フリーランスや個人事業主にとって確定申告は、事業を継続していく上で避けては通れない税務上の手続きです。
事業収入が48万円を超える場合や、副業収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。期限は毎年2月16日から3月15日までですが、早めの準備が重要です。
確定申告の方法は、白色申告と青色申告の2種類があります。特に青色申告は最大65万円の所得控除が受けられ、赤字の繰り越しも可能なため、積極的な活用をおすすめします。
また、確定申告をスムーズに行うためには、日々の収支記録と領収書の保管が欠かせません。最近では会計ソフトを利用することで、経理作業の負担を大幅に軽減できます。
確定申告は複雑に見えますが、基本的な仕組みを理解し、計画的に準備を進めることで適切に対応可能です。不明な点があれば、税務署に相談するか、税理士に依頼することをおすすめします。
(株式会社みらいワークス フリーコンサルタント.jp編集部)
◇こちらの記事もおすすめです◇
「フリーランスでの独立準備!社会保険の基本知識を身に着けよう」
「独立や起業する人は要チェック!助成金をうまく活用しよう」
「起業資金をクラウドファンディングで集めたい!そのために必要な準備とは?」