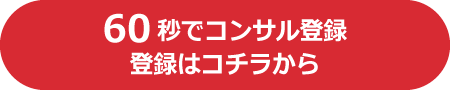中小企業診断士の資格を取得するメリットとは?難易度なども解説

最終更新日:2025/02/04
作成日:2017/02/06
資格には、「就職転職の際に武器となるもの使えるもの」と「就職転職には使いにくいもの」があります。ご自身が目指す方向性を見据え、必要となってくる資格を選び、取得するのがスマートでしょう。
中小企業診断士の資格は、独立やビジネスパーソンとしてのステップアップに有効とされている資格です。今回のコラムでは、中小企業診断士による監修のもと、資格取得によるメリットなどをご紹介します。
※本コラムは、中小企業診断士による監修を行っています。
目次
■中小企業診断士とは?
(1)資格申込者は年2万人を超える
(2)中小企業診断士はフリーランスのコンサルタント向きの資格?
■どんな人が中小企業診断士の資格を取得しているのか
(1)資格取得しているフリーランスは約7割
(2)スキルアップや昇進のために資格取得する会社員も多い
■中小企業診断士の年収
(1)中小企業診断士の平均年収とは
(2)年収を上げる方法とは
■資格を取得する3つのメリット
(1)管理職としての必要な知識が学べる
(2)フリーランスの「看板」のひとつになる
(3)ネットワークを通じて人脈が広がる
(4)起業のハードルが下がる
■資格を取得する2つのデメリット
(1)中小企業診断士の資格における弱い部分
(2)中小企業診断士の資格取得の難易度
■中小企業診断士に向いている人の特徴は?
(1)コミュニケーション能力に優れている人
(2)キャリアアップしたい人
(3)自分の生活スタイルに合った働き方を求める人
(4)勉強が好きな人
(5)柔軟に物事を考えられる人
■中小企業診断士の資格取得までの手段
(1)資格の専門学校に通う
(2)通信教育で講義を受ける
(3)独学で勉強する
■中小企業診断士の試験概要
(1)第一次試験
(2)第二次試験
(3)科目合格制度
(4)他資格等保有による科目免除制度
中小企業診断士とは?

(1)資格申込者は年2万人を超える
2016年に日本経済新聞社と就職転職情報サービスの日経HRが行った調査によると、「ビジネスパーソンが新たに取得したい資格」の第一位は、中小企業診断士とのことでした。ビジネスパーソンによる中小企業診断士への注目はその後も続き、第一次試験の申込み人数は、2017年から2023年まで7年連続で2万人を超えました。
このように、一定のビジネスパーソンからは注目を集めており、中小企業診断士事務所のようなものも設立されているのですが、弁護士事務所や税理士事務所の数と比較すると中小企業診断士事務所の数は圧倒的に少ないのが現状です。
(2)中小企業診断士はフリーランスのコンサルタント向きの資格?
中小企業診断士とは、経産省のホームページによると「中小企業の経営に関する診断・助言について一定の能力を有すると認められる者」と表現されており、経営コンサルタントの役割にとても近しい部分があります。
コンサルタントを必要としているのは、大企業から中小企業、スタートアップ企業までさまざまあります。中小企業やスタートアップ企業の場合、最初から大きな予算を組みコンサルタントチームを設置することは難しいので、一人からでも要請できるフリーランスのコンサルタント人材に白羽の矢が立つのです。
中小企業診断士は、その名の通り、中小企業の発展を目的としたもの。中小企業診断士の資格を保持しているという点は、どんな案件に参画する場合でも、中小企業の目を引くはず。
そのような背景から、フリーランスのコンサルタントにとって、「中小企業診断士の資格は持っていて損はない」と言えるでしょう。
☆あわせて読みたい
『フリーランス人材の悩みとは?業務委託の雇用形態とメリットデメリットを解説』
『【フリーランス入門ガイド】定義や個人事業主との違いとは?増えすぎた理由は?おすすめの仕事や獲得方法とは? 』
『フリーコンサルタントは副業でも稼げる?単価・種類・注意点を解説!』
どんな人が中小企業診断士の資格を取得しているのか
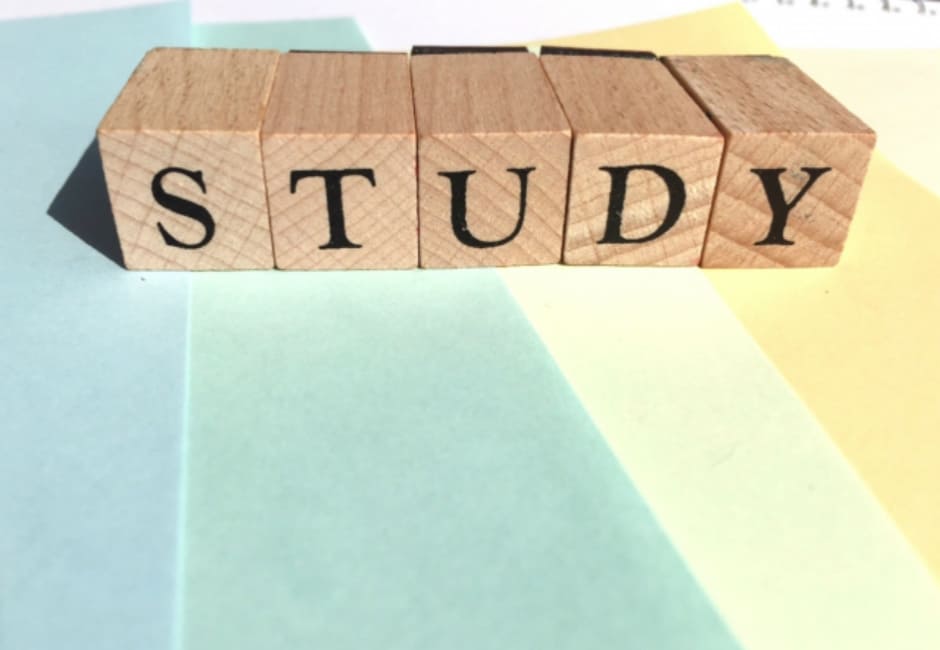
続いて、どのような人が中小企業診断士の資格を取得しているのか、解説します。
(1)資格取得しているフリーランスは約7割
フリーランスでコンサルタントとして活躍する人のどのくらいが、中小企業診断士の資格を取得しているのでしょうか。
社団法人中小企業診断協会が行ったアンケート調査によると、「独立している」と答えた人は約半数の47.8%でした。(※中小企業診断士協会への登録は任意のためあくまで参考値)
独立している人と、独立の意向がある人の数を合わせると、全体の約72.1%になります。
上記のデータのみで考えると、約7割のフリーランスが中小企業診断士の資格を取得しているのではないかと推測できます。
なお、中小企業診断士として認められるのは、登録後5年間。それ以降は更新が必要で、これを怠ると、公に認定された中小企業診断士ではなくなってしまいますので、更新はお忘れなく。
(2)スキルアップや昇進のために資格取得する会社員も多い
経営に関する知識を付けて昇進や年収アップ、社内評価のアップのために資格を取得する会社員も多いようです。
また、50歳を超えた合格者の声では、定年退職後のセカンドキャリアに役立てたいという人も多いと耳にします。
コンサルタントとして独立するために取得する人は、意外と少ない様子の中小企業診断士資格。取得のために学ぶ内容は、「経済学・経済政策」「財務・会計」「企業経営理論」「運営管理」「経営法務」「経営情報システム」「中小企業経営・政策」の7分野で、中小企業に対するコンサルティングを行うために必要な、広範囲でより実践的なものになっています。
☆あわせて読みたい
『【ITコンサルタントとは】激務?学歴や資格は必要?未経験からなるには?仕事内容や年収、SIerとの違いを解説!』
『【フリーコンサル PMO】年収は?必要なスキルや資格は?つまらない?メリット・デメリットも解説』
中小企業診断士の年収
ここからは中小企業診断士の年収を解説します。資格取得後のキャリアイメージを掴んでいきましょう。
(1)中小企業診断士の平均年収とは
厚生労働省によると、中小企業診断士の平均年収は947万6,000円というデータが出ています。国税庁の調査では、日本の平均年収は460万円とされています。つまり、中小企業診断士は、日本の平均の倍以上の年収を得ているということです。
中小企業診断士の資格は取得難易度が高い分、転職やキャリアアップに大きな影響を受けられることが期待できます。
(2)年収を上げる方法とは
中小企業診断士が年収を上げる方法は、ダブルライセンスの取得があげられます。現にファイナンシャルプランナーや社会保険労務士、行政書士などの資格を保持する中小企業診断士は多く存在します。
ダブルライセンスの資格とその取得者の割合は、以下のとおりです。
・ファイナンシャルプランナー:21.7%
・情報処理技術者:17.6%
・社会保険労務士:7.7%
・行政書士:7.4%
・税理士:3.1%
企業経営のアドバイスを行う中で、ファイナンシャルプランナーがあれば財政の知識を、情報処理技術者があればIT・システム面での知識を活かすことができます。
この2つの資格は、今回表にあげた他の資格よりも難易度が低いため、取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
参考:一般社団法人中小企業診断協会|「中小企業診断士活動状況アンケート調査」結果について
資格を取得する3つのメリット

資格を取っても意味がないという意見もありますが、もちろんメリットはあります。4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
(1)管理職としての必要な知識が学べる
勉強面でも受験面でも楽とは言えないこの資格に多くのビジネスパーソン達の注目が集まるのは、講義などの資格を取得するまでの流れの中で管理職としての必要な知識を学べるからです。
たとえば、事業計画書、資金収支計画、資金調達、人事制度作成、リスクマネジメントなど。これまでの仕事で、自分が関わってこなかった未経験の領域を学べる機会になるのです。
資格取得を目指して勉強することが、そのままビジネスパーソンとしての成長の一助にもなるため、転職や独立を検討していない人にとっても、勉強する価値のある資格なのです。
試験概要に関しては、のちに詳しく述べますが、資格取得のための勉強は、そのままビジネスパーソンとしての勉強にあたるとまで考えられます。
つまり、中小企業診断士の資格のための勉強を行なうことで、就職転職に有利になるだけではなく、ビジネスパーソンとして大きく成長することが期待できるのです。
(2)フリーランスの「看板」のひとつになる
フリーランスのコンサルタントにとって資格を取得するのは、仕事の受注にそのまま影響があるという一面もあります。資格を取得して協会に登録をすれば、クライアントに対してわかりやすく自分の実力をアピールできるでしょう。
きちんとアピールできれば、未経験分野の仕事も受注できるかもしれませんし、年収アップも期待できるかもしれません。
また、現在は企業に属しているビジネスパーソンが、将来的な独立や起業のために中小企業診断士の資格を取得することも多いようです。自身のキャリアに中小企業診断士の資格が加われば、鬼に金棒です。
自分自身のブランディングには、中小企業診断士はぜひ取得しておきたい資格と言えるでしょう。
(3)ネットワークを通じて人脈が広がる
中小企業診断士は、中小企業診断協会が開催する交流会や研究会、ビジネス関連の勉強会などでビジネスパーソンと関わりを持つことができます。人脈を広げることで、フリーランスや個人事業主としての仕事獲得につながります。
中小企業診断士が担う経営コンサルティング業務は、他の専門分野の資格保持者に協力を持ちかけることがあり、当然逆のパターンもあります。幅広い業界・職種の人とつながっておいて、損はありません。
(4)起業のハードルが下がる
中小企業診断の資格があると最初の実績を作りやすく、起業のハードルが下がることがあります。
そもそもフリーランスに証明できる実務経験がないと、企業の担当者は「この人に任せられるのかな」と不安を覚えてしまいます。そういった中で中小企業診断士の資格を保持していれば、スキルの証明になり仕事を獲得しやすいでしょう。
また他にも中小企業診断士を取得すれば、企業経営理論や財務・会計、経営情報システムなど起業に必要な知識を得られます。そういった点でも、起業前に取得すべき資格といえるでしょう。
資格を取得する2つのデメリット
メリットがある一方で、デメリットもあります。どのようなデメリットがあるのか把握しておきましょう。
(1)中小企業診断士の資格における弱い部分
中小企業診断士は、独占業務資格ではありません。「業務独占資格」とは、「特定の業務を扱うためには、絶対にこの資格が必要」と法律に定められているものであり、業務独占の領域である資格はそれだけで資格を取得する意味が出てきます。
つまり、「中小企業診断士だからこの仕事ができる」という明確なものはありません。
コンサルタントとして独立を目指すのであれば、資格取得そのものを目標にすることなく、中小企業診断士の試験勉強を通じて得た知識・ノウハウを確実に身に付けることを目標にすることが肝心です。
(2)中小企業診断士の資格取得の難易度
中小企業診断士の試験は、第一次試験と第二次試験の2段階に分けて行われます。実施時期は例年、第一次試験は8月上旬、第二次試験は10月中旬および12月中旬です。
合格率は、第一次試験と第二次試験を同年に受けなくてもいい仕組みになっているため正確には算出できないものの、およそ3~4%程度と言われています。
取得難易度が高いことで有名な資格に弁理士試験がありますが、その弁理士試験と合格率は似たようなもの。暗記型の勉強では合格は難しく、決して低くないハードルです。
ただし、中小企業診断士として正式に登録するには、筆記試験と口述試験からなる第二次試験通過後、15日以上の実務従事、または実務補習の受講が必要。その点でもやはり簡単に取得できる資格ではないと言えそうです。
中小企業診断士に向いている人の特徴は?
ここからは、中小企業診断士に向いている人の特徴を紹介します。特徴が自分に当てはまるのか、今後改善していける特徴であるのかを確認していきましょう。
(1)コミュニケーション能力に優れている人
中小企業診断士は、コミュニケーション能力が高い人に向いています。中小企業診断士の業務は、企業を診断して課題を洗い出し問題を解決することです。その中で顧客の話を聞き、要望を読み取る力は必要不可欠です。
顧客が言いたいことを要約できるスキルや、分かりやすく伝える表現力なども欠かせません。
(2)キャリアアップしたい人
中小企業診断士の取得は、キャリアアップを目指す人に適しています。中小企業診断士の平均年収は947万6,000円と高年収です。中小企業診断士を取得すれば高いスキルが認められ、今よりも高年収を得られる可能性があります。
また、中小企業診断士は、中小企業の経営課題に関する診断や助言を行います。顧客企業の経営に関わるポジションを担うため、責任の重い仕事といえるでしょう。
仕事のやりがいをより一層感じたい方や、ビジネスパーソンとしてキャリアを構築したい方に適しています。
(3)自分の生活スタイルに合った働き方を求める人
中小企業診断士を取得すれば、生活スタイルに合わせた働き方を実現できる可能性があります。
資格は経営コンサルタントやDXコンサルタントなどをはじめ、自治体や公的機関でもその役割が発揮できます。あらゆる職種で役立つ資格である上に、転職にも有利に働きます。
さらに、フリーランスや個人事業主として独立することも可能です。資格を取得すればキャリアプランが広がるといえるでしょう。
中小企業診断士は資格保有者にのみに任される「独占業務」がないため、自由で柔軟な働き方が実現しやすいです。
(4)勉強をすることが好きな人
中小企業診断士は、勉強が好きな人に向いています。資格取得時の学習難易度はもちろん、仕事に就いた後も学習を続けなければなりません。
企業経営のサポートを行う立場として、豊富な知識が求められます。経済や経営に関して関心があることが必須で、最新のニュースなどについての情報収集は欠かせません。
(5)柔軟に物事を考えられる人
中小企業診断士の取得は、物事を柔軟に考えられる人に向いています。自分の考え方に固執せず、企業の立場に立ちながら業務が遂行できると、顧客に重宝されるでしょう。
中小企業診断士は企業の経営改善のために、さまざまな面から俯瞰して観察できる力を要します。
中小企業診断士の資格取得までの手段
ここからは、中小企業診断士の資格を取得する手段を3つ解説します。本章を読み、自分に合う勉強方法を見つけていきましょう。
(1)資格の専門学校に通う
中小企業診断士は、資格取得のための専門学校が複数開校されています。
例えばビジネスの基礎、経営・経理・販売の応用、ビジネスマナーなどが実践的に学べます。基礎から応用、実践までしっかりと知識を固めたい方におすすめです。
専門学校には基礎から応用まで丁寧・着実に学べるカリキュラムがある一方で、学費が年間100万円以上かかることもあります。
(2)通信教育で講義を受ける
中小企業診断士の資格取得を目指すには、通信教育で講義を受ける選択肢があります。自宅でも気軽に取り組める通信講座は、ビジネスパーソンに人気です。
自宅に居ながら隙間時間で学べる上に、カリキュラムが組まれている点が魅力です。カリキュラムは学習の「初心者と経験者」「1次と2次」などによって分かれていることが多いです。
しかし、一定の料金が発生することや、専門学校よりはモチベーションが湧かない人がいることを把握しておきましょう。
(3)独学で勉強する
中小企業診断士は取得難易度は高いものの、独学で合格することも可能です。独学する場合、テキストの選定や勉強のスケジュール管理、隙間時間の活用などが重要となります。
独学であればお金を節約できたり、自分の生活環境に合わせて勉強したりできます。一方で、モチベーションの維持や時間の確保が難しいデメリットもあります。
中小企業診断士の試験概要

中小企業診断士の試験で問われる内容や、合格基準なども押さえておきましょう。
(1)第一次試験
中小企業診断士の試験は第一次試験と第二次試験に別れていて、それぞれの試験日程は異なっています。まずは、第一次試験について説明しましょう。
第一次試験では、資格取得に足る知識を持っているかを判定するため、企業経営に関する下記の7科目について、筆記試験(選択式)が行われます。
1.経済学・経済政策
2.財務・会計
3.企業経営理論
4.運営管理(オペレーション・マネジメント)
5.経営法務
6.経営情報システム
7.中小企業経営・中小企業政策
上記の分野に未経験の領域がある場合、やはり独学では厳しいでしょう。学校に通うなどして、未経験分野の知識を深める必要があります。
(2)第二次試験
第二次試験では、第一次試験で問われた知識の応用能力を判定するため、「組織(人事含む)」「マーケティング・流通」「生産・技術」「財務・会計」の4事例が出題され、それを診断・助言する筆記試験と、中小企業の診断および助言に関する能力を問う口述試験が行われます。
(3)科目合格制度
第一次試験に「科目合格制度」および「他資格等保有による科目免除制度」が設けられています。まずは、科目合格制度について説明しましょう。
中小企業診断士の第一次試験は、受験科目の総合得点が60%以上、かつ40%未満の科目がひとつもない場合に合格。
ただし、「総合得点は60%を超えたが40%を切ってしまった科目があった」、あるいは「総合得点は60%に届かなかったが60%を超えた科目もあった」という場合は、試験委員会が認めた得点比率を達していれば、60%を達した科目のみ合格になります。
翌年と翌々年の2年間にわたり、合格科目の受験は免除申請ができます。これが「科目合格制度」です。まとめて7科目受験するほどの勉強時間が取れない人でも、計画的に2~3科目ずつ取得していけるのが、科目合格制度の大きなメリットです。
ただし、デメリットもあります。合格した科目の受験が順次免除になると、翌年、翌々年は苦手な科目が残っていく可能性が高いため、平均60点というハードルが高くなってしまうという点。
ただし、合格科目の受験を免除してもらうかどうかはあくまで受験者本人が決めることであり、免除申請をせずに再受験することもできます。
よって、実際に受験する際には、単に「免除してもらえるものは免除してもらおう」ということではなく、例えば既に合格していて免除申請もできる科目を敢えて再受験することで平均点を上げる、といった戦略が必要になってくると考えられます。
(4)他資格等保有による科目免除制度
続いて、「他資格等保有による科目免除制度」についてです。
他資格等保有による科目免除制度とは、特定の職に就いている、もしくは特定の資格を保有している場合に限り、証明書類を提出することで、7科目中の一定の科目の受験が免除されるというもの。科目別の免除対象職種・資格保持者例は、下記の通りです。
1)経済学・経済政策 :公認会計士試験「経済学」科目合格者、不動産鑑定士など
2)財務・会計: 公認会計士とその試験合格者、税理士とその試験合格者など
3)経営法務 :弁護士、司法試験合格者など
4)経営情報システム :技術士、特定の情報処理技術者試験合格者など
資格による免除も、申請をするかどうかは受験者に委ねられているため、敢えて受験するという選択もできます。
まとめ
中小企業診断士の勉強では、事業計画書、資金収支計画、資金調達、人事制度作成、リスクマネジメントなどを学びます。今までの経験から「身につけている」と思っていることでも、中小企業診断士のための勉強として改めて知識をチェックすると、意外と自分の知識に穴があることに気づかされることもあるでしょう。
就職や転職に関してはもちろん、昇進や年収アップ、就職や転職、経営コンサルタントとしての独立にも一役買ってくれる中小企業診断士の資格。自分の能力や領域を見つめなおすきっかけにもなることでしょう。
あなたも中小企業診断士になって、周りから一目置かれる存在になってみませんか。
(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)

< 監修者プロフィール >
大野 晴司(おおの せいじ)
東京都立大学(現首都大学東京)卒業後、日産自動車で国内のマーケティング部門や系列ディーラーでの営業マンや本社販促部署長などを経験。中小企業診断士資格取得のために退職、2003年3月資格取得。その後、マーケティングリサーチ会社、自動車関連メーカーを経て、2008年にビズ・エキスパート株式会社を設立。神奈川・東京の中小・中堅企業の営業力・マーケティング力支援のほか、経営企画業務、新規事業支援を主な事業として活動中。また、企業向けセミナー講師なども務める。
ビズ・エキスパート株式会社:http://b-ex.biz/index.html
プロフェッショナリズムインタビュー:https://freeconsultant.jp/workstyle/w020
◇こちらの記事もおすすめです◇